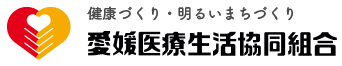- 2019.05.10 トップニュース
- 豪雨災害の南予を行く ~被災地のいまを見て~
生協ブロック社保・平和委員会は毎年社保学校を開き社会保障の充実や平和の大切さを学ぶ取り組みをしています。今年は三月三十一日に、洪水被害のあった大洲・肱川地域に被災地復興支援のツアーを行い、46名の組合員が参加しました。

憲法9条の碑の前で
爪痕残る洪水被災地
昨年7月の西日本豪雨では大きな被害が出て、県内でも28名の方が犠牲になり、大洲市では約4600戸が浸水被害に遭いました。豪雨から8ヶ月以上が過ぎましたが、復興はまだ十分ではありません。
はじめに大洲市の道の駅「愛たい菜」で買い物をし、郷土史研究家で大洲9条の会の澄田恭一さんに大洲・肱川地域の豪雨被災地の案内をしていただきました。徳の森に建設された、2年間居住可能な48戸の仮設住宅を見学した後、一帯が水に浸かった菅田地区を訪問。鹿野川ダムの大量放水後は、あっという間に頭まで水が押し寄せたということでした。鹿野川ダムの近くでは大きく陥没したままになっている道路や流された家屋の跡、被災したまま住めなくなった住宅などを見て被害の大きさを実感しました。泥まみれの家財が放置されています。もしこれが我が家だったら…との思いが消せません。
医療生協からも支援
医療生協からは延べ56人が支援活動に参加し、泥出しや後片付けに汗を流しました。澄田さんによると、被災後は多いときで一日に1100人もの支援のボランティアが来て復興に協力し、地元の人たちに喜ばれました。中には、曹洞宗の僧侶が毎日被災者を励ます話をして感謝されたということです。いろいろな支援の仕方があるものだと思いました。

仮設住宅
桜満開の「風の博物館」で
昼に訪れた「風の博物館」では、館長代理の河野信介さんから野村町にある自宅の被災などを記録した映像や写真パネルが紹介されました。自宅前の道路に水が流れ込んで水かさが増していく様子も記録されています。隣に住んでいたお母さんを助けに行ったときは水かさが増し、立つことができず泳いで九死に一生をえました。二軒隣は二人が亡くなりました。急な豪雨の恐ろしさは一生忘れることはないと話してくれました。
石碑に彫られた9条を読む
憲法9条を守る大洲の会によって、県内初の「憲法9条の碑」が昨年大洲市内に建立されました。参加者のみなさんは石碑に刻まれた9条の条文をあらためて読み直し、平和を守るとの思いを新たにしました。石碑の裏には制作者の玉井義幸さんの「子供達の叫び」と題した詩も彫られています。
交流深める学習の機会
このツアーはお互いに交流を深め、普段は知らずに車で通り過ぎるところを、現地の歴史や事情に詳しい方に案内をしていただきます。興味が増し知識がいっそう深まるのが、ただの名所巡りとは違う社保平和バスツアーの魅力です。案内をしていただいたので、被害を自分の事としてとらえることができました。同じ愛媛県民として何ができるのか考え行動したいと思います。この豪雨災害を決して忘れることなく、防災意識を高め、人災は決して起こしてはなりません。

愛たい菜
(文・梶原 健市)